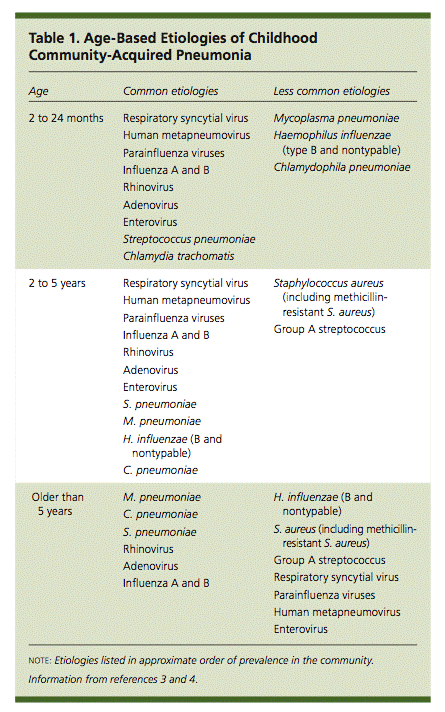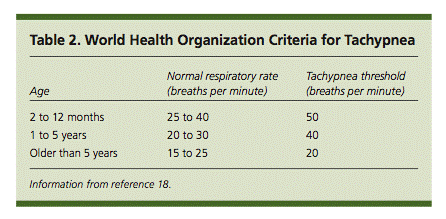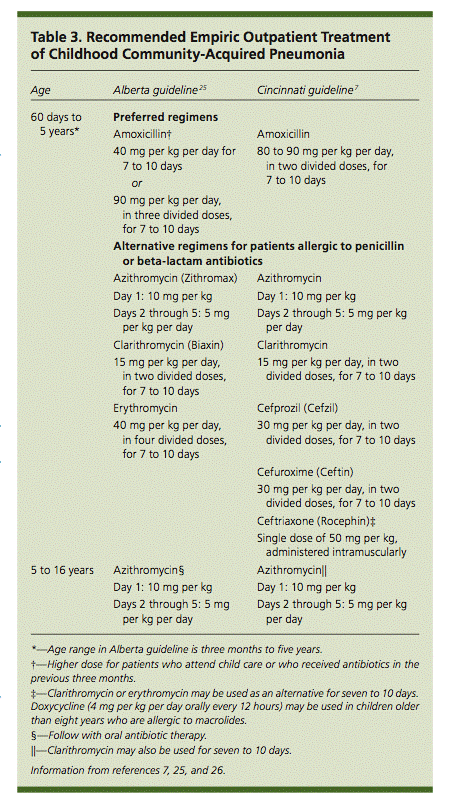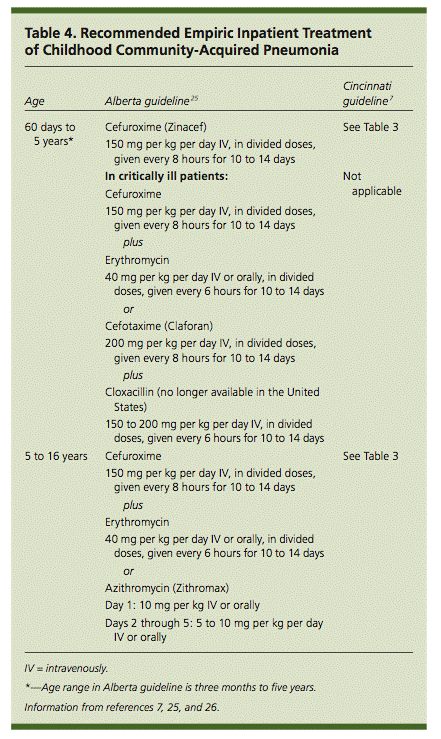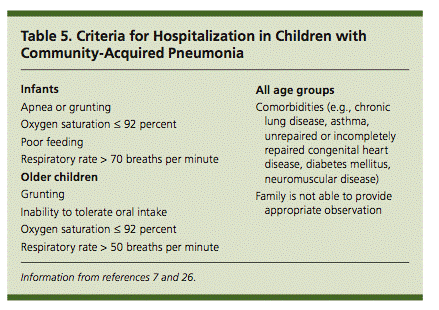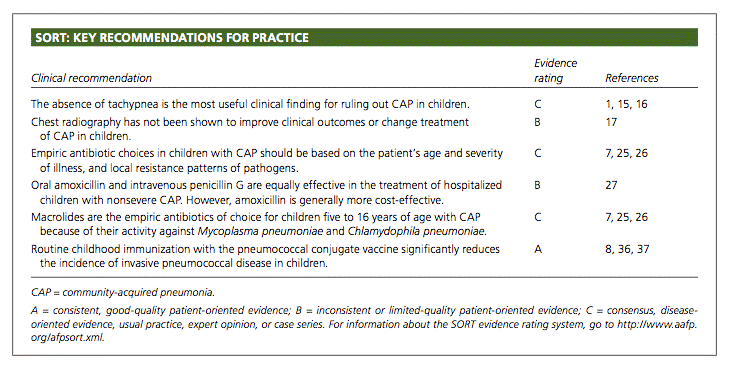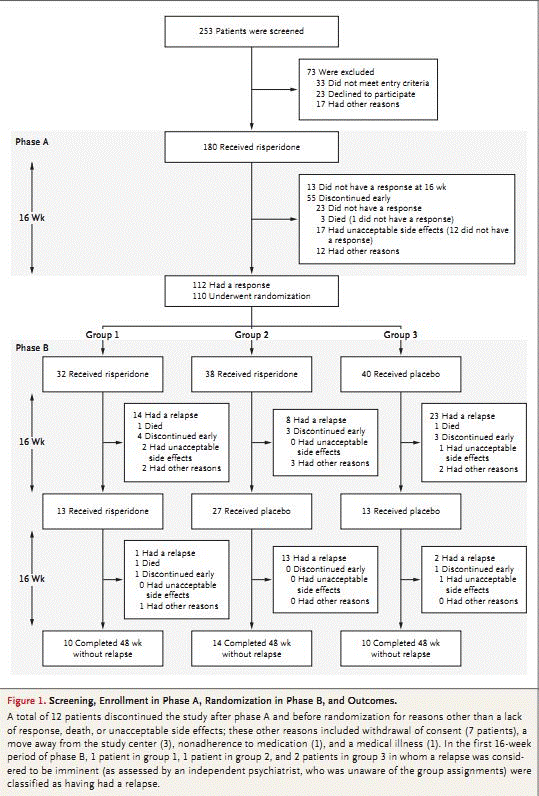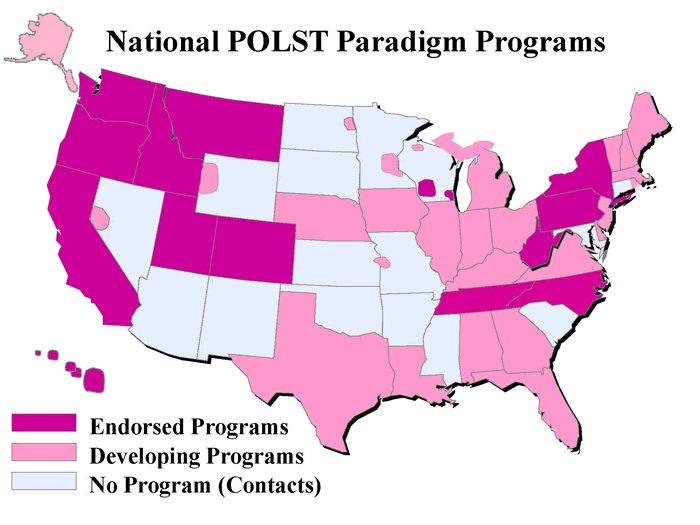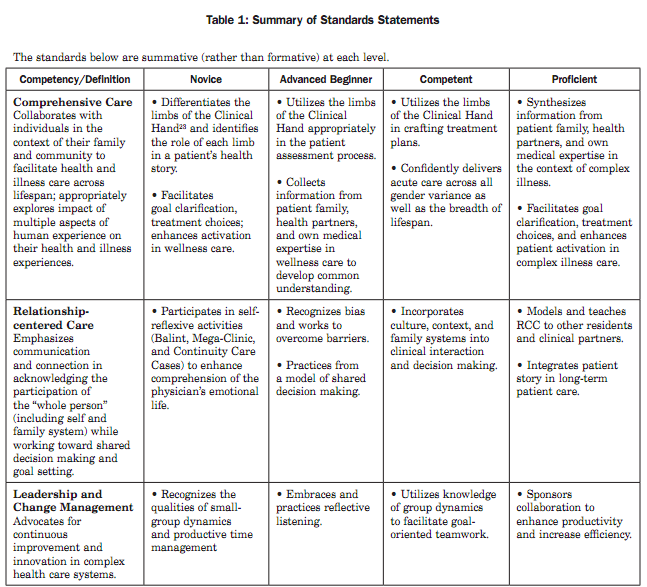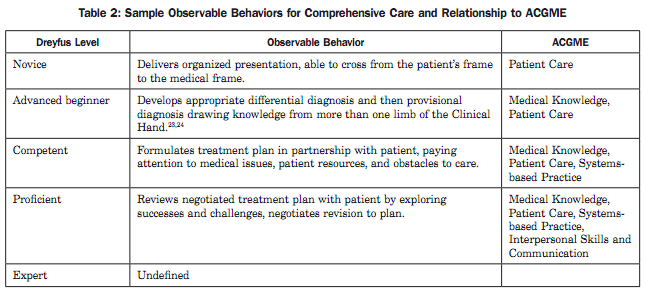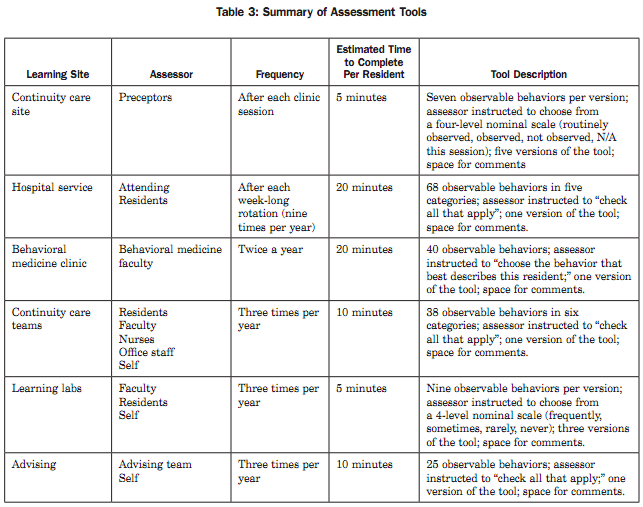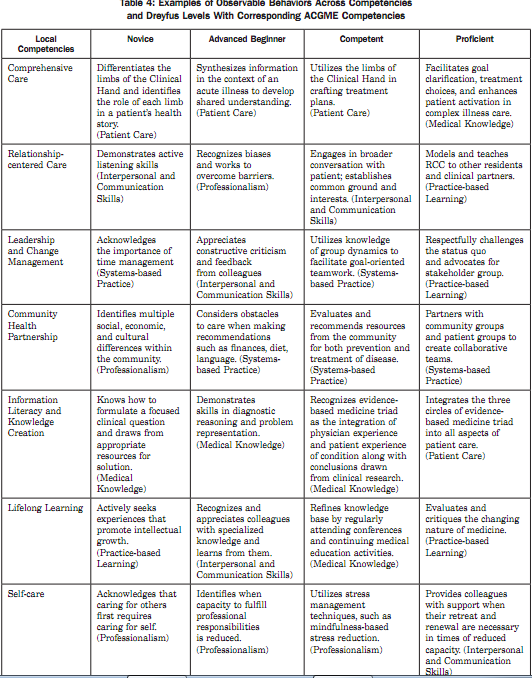- 文献名 -
Mark S Pearce et al:Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study.Lancet. 2012 August 4; 380(9840): 499-505.
- この文献を選んだ背景 -
当診療所ではCT検査が可能である。年に数人は小児のCT検査を施行することがある。今回CT検査から受ける放射線により、白血病、脳腫瘍の発生に対する影響を評価するコホート研究が発表されたため、紹介したい。
- 要約 -
【背景】
CTは臨床的に非常に有用である一方で、電離放射線に関連した潜在的な発癌リスクが存在する。しかも大人よりも子供は放射線への感受性が強い。今回子供と若年成人のコホートでCTスキャン後の白血病と脳腫瘍の存在を評価したい。今までCT施行後の患者における発癌リスクの直接的な研究はなかった(新奇性)。
【方法】
後ろ向きコホート研究で、1985年から2002年にイングランド、ウェールズ、スコットランドのNHSにおいてCT検査を受けた、当時22歳以下の方で、過去に癌の診断を受けていない患者を対象とした。1985年1月1日から2008年12月31日までにNHS名簿から癌発現率、死亡、フォローアップ不能のデータを採取した。CTスキャンごとに脳と赤色骨髄に吸収された線量(mGy)を計算し、ポワソン相対危険モデルで白血病と脳腫瘍の過剰発現を評価した。癌を疑った際の診断目的に施行されたCTの算入を避けるため、初回のCT検査から白血病の診断に至った期間が2年間、脳腫瘍であれば5年間以下の者は除外した。
【結果】
追跡期間中に178,604人の患者のうち74人が白血病と診断され、176,587人の患者のうち135人が脳腫瘍の診断に至った。CTスキャンと白血病に関連のある放射線濃度はERR/mGyは0.036(95%CI0.005-0.120;P=0.0097) であり、脳腫瘍では過剰相対リスク0.023(0.010-0.049;P<0.0001)であった。5mGy以下の線量を受けた患者と比較して、少なくとも累積30mGy(平均51.13mGy)の被曝をした患者では白血病の相対危険度は3.18(95%CI1.46-6.94)であった。また累積50-74mGy(平均60.42mGy)の被曝をした患者では脳腫瘍の相対危険度は2.82(1.33-6.03)であった。
【解釈】
小児が約50mGy(脳CT5~10回)の累積被曝をした場合、白血病のリスクが約3倍で、脳腫瘍においては約60mGy(脳CT2~3回)で3倍になる。これらの癌はまれなものである故、累積寄与危険度は低い。10歳以下の小児で初回のCT検査から10年間において考えてみると、10,000回の頭部CT検査で1人の白血病、1人の脳腫瘍が生じる計算となる。臨床的な利点が相対危険度を上回ることは確かだが、CT検査の放射線濃度は可能な限り低く保つべきあり、妥当性があるのであれば電離放射線を生じない他の方法を考慮すべきである。
参考
相対リスク(RR)と過剰相対リスク(ERR)
一般的な疫学研究において2つ以上の集団でリスクを比べる時、非曝露群と比べて曝露群が「何倍」のリスクがあるのかをみるのが相対リスク(RR: relative risk)で、1以上であれば曝露群のリスクが高く、1以下であれば曝露群のリスクが低い。例えば、被曝線量がゼロの集団における疾患Aの発生リスクが10万人あたり2人で、被曝線量が1 Svの集団では10万人あたり5人だった場合、単純なRRは5/2=2.5倍となる。しかし、放射線被ばくのリスク評価では、放射線を浴びることによって単位線量当たりどのくらい過剰にリスクが上昇したのかをみる過剰相対リスク(ERR: Excess relative risk / 1Sv)という指標が用いられることが多い。上記の例では、単純なERRは(5-2)/2=1.5となり、被曝線量1 Sv浴びると1.5倍過剰に発生リスクが上昇することを意味する。しかし、実際の被曝者集団における解析では、被ばく線量、被ばく時年齢、被ばくからの経過時間、現在の年齢、性別などの、様々な因子を考慮して解析されている点に注意が必要である。
開催日:2012年8月29日